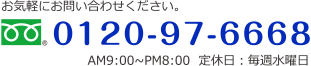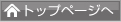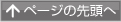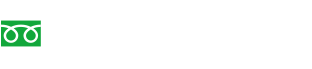- ・抵当権の抹消
- ・引越し・境界の確認
- ・登記・引渡し時に必要なもの
- ・登記・引渡し
- ・引渡し後の手続き
抵当権の抹消
住宅ローンを返済中で、物件に抵当権が設定されている場合が多く、抵当権の抹消の準備をしておかなければなりません。抵当権とは、簡単に言えば「担保」のことです。
住宅ローンなどを組んだ場合は、ほぼ必ず購入した土地と新しく建てた家に
抵当権という担保をつけることになります。
住宅ローンを貸し出した銀行が、住宅ローンという債権を保全するために、住宅ローンで購入した不動産に抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、銀行は住宅ローンの返済が滞ったときに抵当権を実行して、その物件の競売を申し立てることができるのです。
銀行は抵当権を実行して競売することで、滞った住宅ローンの未返済部分を返済してもらうことができるようになります。
抵当権の特徴は、抵当権が設定されても
債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がないことです。
そのため、所有権者は抵当権を設定した物件を自由に利用・収益・処分ができるので、
住宅ローンの場合でもマイホームに自由に住んで、改築して、売却することができるのです。
なお、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになります。
通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定されます。
つまり、債務者=抵当権設定者となるわけですが、
債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もあります。
たとえば、お金を借りるために親の土地を担保にしてもらうケースなどです。
売却代金の決済日が決まったら、
住宅ローンを借りている金融機関で抹消の手続きをしておきます。
売却代金の決済日の当日に売却資金から住宅ローンの残金を振り込みます。
その後、抹消の書類を司法書士と一緒に取りに行きましょう。
この繁雑な業務も私たちパティーナがご相談承り、お手伝いをさせて頂きますので、ご安心ください。

引越し・境界の確認
売買契約(又は仮契約)が済み、引き渡し日が決まれば、次の手順で準備を進めていきましょう。売却物件がまだ居住中の物件であった場合は、日程にあわせて引っ越しの準備を始めます。
一戸建てや土地の場合は買主様に境界の位置を明示し、
売却物件の詳説をする必要があります。
買主様と一緒に、図面などを見ながら、現地で境界の確認などをします。
もし、時間の経過などで周辺の環境が変わってしまったなどの理由から境界の位置が不明な場合は、土地家屋調査士に依頼して境界の位置を確定させておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。
買主様に引き渡せるよう、パンフレットや取扱説明書、保証書などをまとめておくのも重要な事のひとつです。
いざ使い始めたら、ガス湯沸かし器の使い方がわからない、
洗濯機の設置方法がよく理解できない、
庭の外灯の電灯の変え方がわからない、などなど、案外困りごとが発生するものです。
そうした際に、やはりすべての備品の取り扱い説明書がひとまとめにしてあるとスムーズにすすめることができます。
周辺地区のゴミ捨てや、自治会、公共施設の案内などもひと目でわかるものを用意するか、
引き渡しや確認作業の際にメモ書きを渡したいですね。
口頭だけで伝えるのは不親切ですから、避けたいところです。
引越しが終われば掃除をし、買主様に気持ちよく引っ越して来ていただきましょう。
基本的には、売却物件に対して、キズの補修や劣化部分の修復までする必要はありません。
引き渡し前に買主様に現地最終確認をしていただき、いよいよ引き渡しという最終工程に入ります。
売却テラスでは、引越し・境界の確認時のアドバイスやサポートも行っております。

登記・引渡し時に必要なもの
登記・引渡し時に必要なものは、以下のとおりです。- 仲介手数料
(正規手数料:物件価格の3%+6万「税別」) - 抵当権抹消費用
(司法書士に支払う金額:一筆抹消につき1万~2万円)
※抵当権の設定の登記をした後,借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅します
が、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、
抹消登記(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ります。
抵当権を抹消するために、
登記権利者(抹消の登記をすることによって利益を受ける人(土地や建物の所有者))と
登記義務者(抹消の登記をすることによって権利(抵当権)を失う者(銀行などの抵当権者))が
共同で登記をすることになります。
仮に一人で登記ができるとなれば、お金を返してもらっていないのに
抵当権の登記が知らぬ間に抹消されては困るからです。
- 権利書(登記済証または登記識別情報通知) ※不動産について登記が完了した際に、
登記所が登記名義人に交付する書面で、権利証と呼ばれるのはこのことです。
もしも紛失している場合、司法書士にこれにかわる手続きを依頼しますので、別途費用が必要となります。
次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、
不動産取引に必要な書類です。
登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、
登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための
本人確認手段のひとつでもあります。
現在では不動産登記法改正により、2005年3月7日より「登記済証」は
オンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わることとなりました。
- 実印
- 印鑑証明(発行より3カ月以内)
- 鍵一式
- 関係書類(パンフレットや取扱説明書、保証書など)
- 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
パティーナでは、登記・引渡し時の各種手続きのご案内と合わせて、手続きに必要なもののサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

登記・引渡し
当日中に法務局に登記手続きを済ますため、登記手続きの書類作成を平日の午前中に、
買主様の住宅ローン借入先の金融機関で行います。
引渡しの流れ
基本的に登録などの手続きは、その殆どを司法書士が行います。- 1.該当物件に抵当権が抹消できる書類が揃っているかを確認します。
- 2.買主様の所有権が移転できる書類がそろっているか確認します。
- 3.書類に問題がなければ買主様の住宅ローンが実行されます。
- 4.残代金を受領したら、物件の鍵と関係書類を買主様にお渡しします。
- 5.司法書士が法務局にて抵当権の抹消の手続きと所有権移転の手続きをします。
司法書士とは・・・
司法書士とは、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定された業務を行う
有資格者で、およそ次のような内容の業務を扱います。
-
【司法書士の主な業務】
- 登記又は供託手続の代理
- 地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、
(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成 - 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、
民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談 - 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
などです。
司法書士は、不動産会社がご紹介しますが、
お客様の方にお知り合いの方がいるという場合には、
その方にやっていただくのは何の問題もありません。
事前にお知らせいただき、手続きのご相談を行っていきます。
パティーナでは、登記・引渡し時のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

引渡し後の手続き
おめでとうございます。売却物件の売買契約は終わり、所有権移転の手続きも完了しました。
今までは売主様の所有だった物件も、今では晴れて買主様の所有となり、
売主様から買主様へと引き継がれたのです。
いよいよ鍵を引き渡した時点で、売却は完了、
そして愛着のある"我が家"ともお別れする事となります。
あと残っている作業と言えば、司法書士や売却を依頼した仲介業者に報酬や手数料を支払うだけです。
しかし、ここで敢えて最後にやっておくべくことをお話しておきましょう。
不動産の購入は、人生でそう何度も経験することではありません。
そんな数少ない経験において買主様とご縁を持つことができました。
買主様に対して、「購入してくれたことに対する感謝」の思いを形にしませんか?
せっかくのご縁なのですから、今後に続く良い人間関係を築いておいても損はないでしょう。
「値引きもしたし、十分なことはしたつもりだ!」
いやいや、そんな事はおっしゃらずに。
例えば、買主様が今後も大事にしてくれそうなものを置いていってはどうでしょう?
せめて、すぐ使えるような消耗品だけでも置いておけば?
感謝の気持ちを表す短い手紙などいかがでしょう。
もし、その買主様に気に入ってもらえず購入してくれていなかったら...。
そう考えると自然に感謝の気持ちが持てると思いますよ。
ビジネスと考えれば、売る方も買う方も気持ちが良い状態、Win-Winの関係で終わりたいものですよね。
売却価格でも、取引の段取りでも、そして契約でも、
感情的にも、全ての面でよい関係が築けるような取引をしたいものです。
相手の立場に立って考えれば、不動産売却は自ずと成功へと導かれていくものなのです。
パティーナは、気持ちの良い不動産取引が叶うよう、皆様のパートナーとして努力してまいります。